
スキルアップをするにはさまざまな方法がありますが、インプットとアウトプットをバランスよく行えるものとしておすすめなのが、技術ブログの作成です。
ITエンジニアのスキルアップ方法について解説をした記事がこちらです。
ITエンジニアにとって、技術ブログを作成することはメリットづくしといっても過言ではありません。
たとえば
などがあります。
 ウリ
ウリ自らの知識やスキルを発信することで、自分にとっても読者にとってもメリットはたくさんあります。
こちらの記事では、ITエンジニアが技術ブログを発信するメリットや書く内容、使用するサービスなど技術ブログの始め方について解説します。
この記事を読んで、ブログ作成に前向きになり一歩を踏み出すITエンジニアの人が増えると嬉しいです。
技術ブログを発信するITエンジニアは多い
ITエンジニア界隈のインフルエンサーや有名な人で技術ブログをやっている人は少なくありません。
その一例を紹介したものがこちらです。




Lean Baseball
URL:https://shinyorke.hatenablog.com/
外資系コンサルティング会社でエンジニア系マネージャーを務めるの中川伸一さんのブログです。
「全世界に公開して良いメモ帳」と銘打ち有益な情報や野球データ分析は興味深く見ています。
ちなみに、僕の書いているブログはこんな感じです。


GKテックブログ
僕がマイペースで更新している技術ブログです。
技術面で勉強したことの備忘録、また転職や独立して事務所を契約した時のことを書いています。
そもそも技術ブログって何?
技術ブログとは、ITエンジニアが何かしらの技術や情報についてノウハウをまとめたものです。
プログラミングの解説や開発ノウハウ、最新の技術トレンドなど、自分が得た知識を発信して読み手に共有して活用してもらうためのものです。
内容はメジャーなものもいいですし、その反対に情報量の少ないマイナーな領域のものでも問題ありません。



特にマイナーな技術領域の場合は情報量自体が少ないので、その技術領域で困っている人にとってはとてもありがたい存在となります。
ITエンジニアが技術ブログを発信することは、自分にとってもブログの読者にとってもメリットは多いです。
ITエンジニアが技術ブログを発信するメリット
ITエンジニアが技術ブログを作成することでさまざまメリットがあります。
同じ悩みを持つ誰かの役に立つ
仕事を進める中で課題が生まれ、その都度解決方法を調べながら対処しているかと思います。
エンジニアリングに関する知識やスキルをブログ記事として残すことで、自分以外のエンジニアが同じような悩みや課題を持った時に参考にすることができます。
自分の身近にはいないかもしれませんが
- 同じ悩みを抱えるエンジニアの悩みを解消できるかもしれない
- 公開した知識やスキルを必要としてくれる人がいるかもしれない
自分が誰かのブログを見て解決策を見つけることがあるように、その反対も然りです。
同じ悩みを持つエンジニアの一助になる、と考えればモチベーションも上がるのではないでしょうか。



技術ブログの記事を読んでくれて、その感想をコメントやXでもらったりすると嬉しいです。
自分という商品のアピール材料になる
技術ブログで発信を行うことは、自分という商品をアピールすることにもつながります。
ブログの場合はドメインが育って記事を読んでもらえるまでに時間がかかるものの、コツコツと続けていけば次第に自分と同じような技術領域の人に認知されはじめます。
XなどのSNSと組み合わせて発信をしていくことで、自分の人となりを知ってもらうツールにもなるでしょう。
インプットとアウトプットをバランスよくできる
技術ブログを書くにはインプットした内容をアウトプットする必要があるので、双方向に情報の出し入れをすることで思考の定着につながりやすいです。
また、見えない相手に向けてブログを書くので、理解してもらう工夫をするので思考の整理にもなります。
定期的に脳の情報を技術ブログという「保管庫」に移し替えることで、脳に新しいスペースを作って新たなインプットすることができます。



僕も過去に経験した内容や習得した技術をブログに書くことで、頭の情報をブログに移し替えて保管するイメージがあります。
転職活動や案件獲得に役立つこともある
技術領域にもよりますが、技術ブログは意外といろいろな人が読んでくれるため、技術ブログがきっかけで他のITエンジニアに認知されたり転職活動に役立つことがあります。
技術ブログでセルフブランディングすることもできるので、積極的に情報発信ができる人材として転職活動では評価されることが多いです。
また、技術ブログを読んでいくとや書き手のスキルがある程度理解できるので、スキルを頼って仕事の依頼が来ることも少なくありません。
そっか。技術ブログ自体がその人の職務経歴書やポートフォリオみたいになるんで採用企業や仕事を振る側もわかりやすいよな・・



そこにプラスをして、


ウリの体験談
〜技術ブログを書いていることは意外と評価される〜
転職活動において技術ブログを書いていることは評価される傾向にあります。
事業会社で採用に関わっていた際は、求職者がどのような情報発信をしているかは気にしましたし、会社としても技術ブログを書いていることをとても評価していました。
技術ブログを書くと評価される理由は、積極的に情報発信をする行動力やエンジニア界隈に積極的に貢献するポジティブさとして受け止められるからです。
これは技術ブログだけでなく、GitHubやGitLabなどに自身で書いたソースコードを公開していることも同様に評価されます。
とりあえず半年くらい自分が気になる領域のことを書いていると、その領域を調べる人たちによって検索上位に出てくるでしょう。
また、X上で勝手に拡散されていて、色々な人に見てもらえることもあります。
転職活動を意識しなくても、定期的に何らかの技術的なアウトプットを世の中に発信することは、ITエンジニアとしては大事なことです。
広告掲載で収益化もできる
広告を技術ブログ内に掲載をすることで収益につなげられることがあります。
僕が技術ブログでやっていたのは、Amazonアソシエイトです。
AmazonアソシエイトとはAmazonが提供するASPで、自分が読んで良かった本のレビュー記事をブログで書いて、そこに広告リンクを貼り付けていました。
技術ブログの記事が読まれてリンクを経由して購入してもらうと、自分の報酬となる仕組みです。
簡単にも思えますが、安定して収益を得るにはまずブログにアクセスしてもらう必要があります。
継続的にブログへアクセスしてもらうには、SEO施策や定期的な各記事のメンテナンスなど手間がかかりますし、最低でも半年くらいは必要です。
収益化はラクとは言い難いですが、コツコツと地道に続けていけば安定した収益化も夢ではありません。



コツコツ続けていると、たまにブログ記事を読んだ人が広告リンクを踏んで購入してくれることもあって、お小遣い程度にはなってます。
技術ブログを書くことにメリットがたくさんあることは分かったのですが
どんなことを書いたらいいのか分からない・・
そう思っている人も多いのではないでしょうか。
技術ブログには何を書けばいいのか
技術ブログに書く内容は、個人のブログなので基本的には何を書いてもOKです。
とは言うものの、技術ブログを書いたことがない人は
などを見て、世の中のITエンジニアがどのような技術ブログを書いているのか見てみましょう。
またそれ以外にも
- 仕事で関わっている技術的なことの備忘録
- 個人開発でやっていることの備忘録
- はじめて触ってみたサービス(パブリッククラウド、SaaSなど)についての感想
などからはじめても、書きやすいかなと思います。
ウリがおすすめする技術ブログのはじめ方
はじめて技術ブログを書く場合、環境構築の手順などがおすすめで、DockerやGit/GitHubの環境構築などは過去にいろんな人が記事を書いている内容です。
しかしサービス自体は常にアップデートし続けるため、サービスのUIが変更するなどして過去の手順が使えないケースが少なくありません。
また、そんなに難しくない内容でも年に1、2回くらいしかやらない作業は正確に覚えている人は少ないです。
そんな場合、多くのITエンジニアはGoogle検索で出てきた情報をもとに作業するケースが多くなります。
まずは過去に手順を書いている人の記事を参考にして、自分自身で最新の手順を作ってみるところからはじめると、ハードルが低くて挫折しずらいです。
上記過程をステップ方式でまとめると下記になります。
途中で挫折をしないように、自分はなぜ技術ブログを書くのか、その目的を明確にしましょう!
- 自分が学んだ内容の備忘録として
- 副業としての収入を得るため(目標:月5万円)など
何について書くのかテーマを決めて、その情報を集めましょう!
- おすすめなのは環境構築の手順など
- DockerやGit/GitHubの環境構築などは過去に取り上げている人が多いので参考にする
過去に手順を書いている人の記事を参考にして、自分自身で最新の手順を作ってみるところからはじめましょう。
実際に手を動かすことで、タイトルや見出しの設定、アイキャッチ、画像の挿入などを覚えてください。



使い方の手順でブログ記事を書く場合、各工程の画像を入れていくと簡単な説明だけでも記事がそれなりの見栄えになるのでおすすめです。
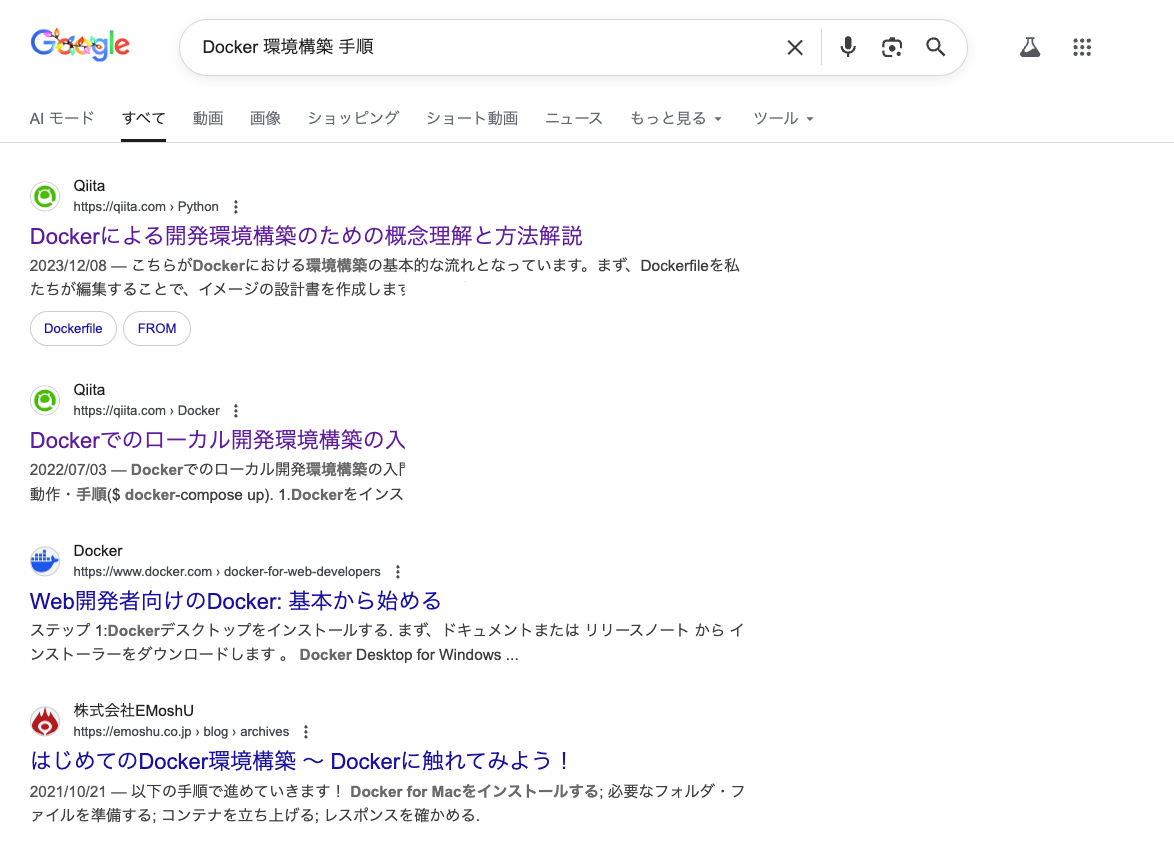
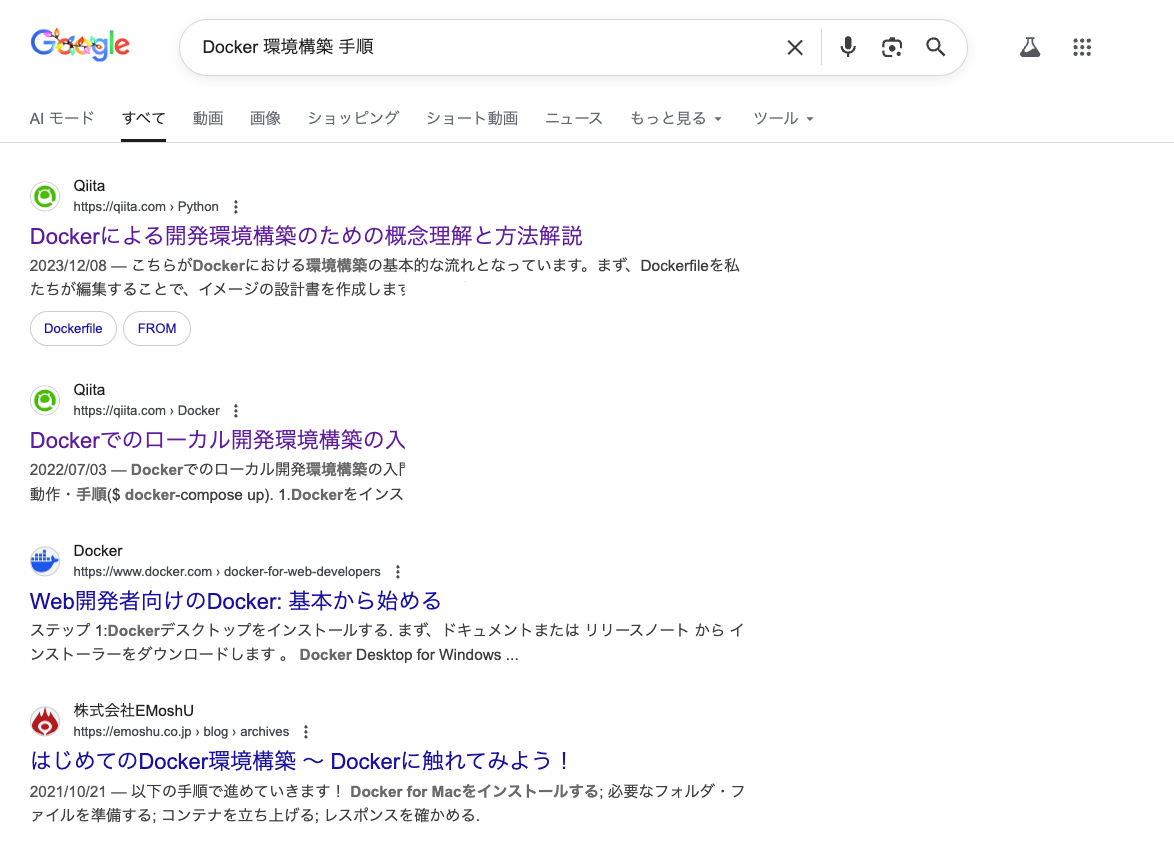
環境構築の手順はブログを挙げている人が多いので、自分がいいと思う人のやり方を踏襲するのが良い。丸パクリは厳禁なので注意しよう!!
利用するブログサービスはどうするべきか
技術ブログをはじめようとする時に、利用するプラットフォームはいくつかあります。
すぐに書きはじめたいの場合は、QiitaやZenn、はてなブログなどがおすすめです。
ただ、副業としてブログで広告収入などを得たいのであれば、ConoHa Wing
![]()
![]()



無料ブログでは、広告が自由掲載できず収益化がしにくかったり、自身の広告がクリックされにくかったりするのでおすすめしませんね。
ちなみに、僕がおすすめするレンタルサーバーはConoHa Wing
![]()
![]()
一般的に技術ブログはお金にならないと言われていますし、そもそも儲けようとしている人はあまりいないような気もします。
技術ブログの内容に関連する技術書をAmazonアソシエイトのリンクと合わせて貼っておくと、閲覧者が増えてくるとそこそこ買ってくれます。
月に3〜5本くらい記事を更新し続けることができれば毎月数千円から多くて数万円程度は目指せるので、サーバー代の元が取れるくらいにはなるでしょう。
【コラム】技術ブログをはじめるならQiitaか?ブログか?


結論を先にお伝えをすると、それぞれの特徴を踏まえた上でどちらを判断するのかは、情報発信の目的や何を優先にするかによって選んでいただきたいです。
ブログがQiitaよりプラスな点は
その反面、Qiitaよりもマイナス、大変な点はこちらです。



カンタンにお伝えするなら、人とつながりたいならQiita、収益化も視野にじっくり取り組みたいならブログでしょうか。
まとめ|ITエンジニアが技術ブログをするのは良いことづくめ
技術ブログで発信するITエンジニアは増えていますし、下記のようなメリットがたくさんあります。
- 同じ悩みを持つ誰かの役に立つ
- 自分という商品のアピール材料になる
- インプットとアウトプットをバランスよくできる
- 転職活動や案件獲得に役立つこともある
- 広告掲載で収益化もできる
特に技術ブログは読み進めると書き手のスキルや人となりがわかるので、転職活動でのアピールやフリーの場合は案件獲得に役立つのは大きな魅力でしょう。
技術ブログで何を書いたらいいのか迷った場合は、過去に手順を書いている人の記事を参考にして自分自身で最新の手順を作ってみるところからはじめると、進めやすいのでおすすめです。
ブログサービスについては、人との繋がりを大事にしたいならQiita、じっくり収益化も視野に入れて取り組むならブログを選びましょう。
ブログ以外にもXを活用してスキルアップをする方法があります。
詳細を知りたい人はこちらをご覧ください。
