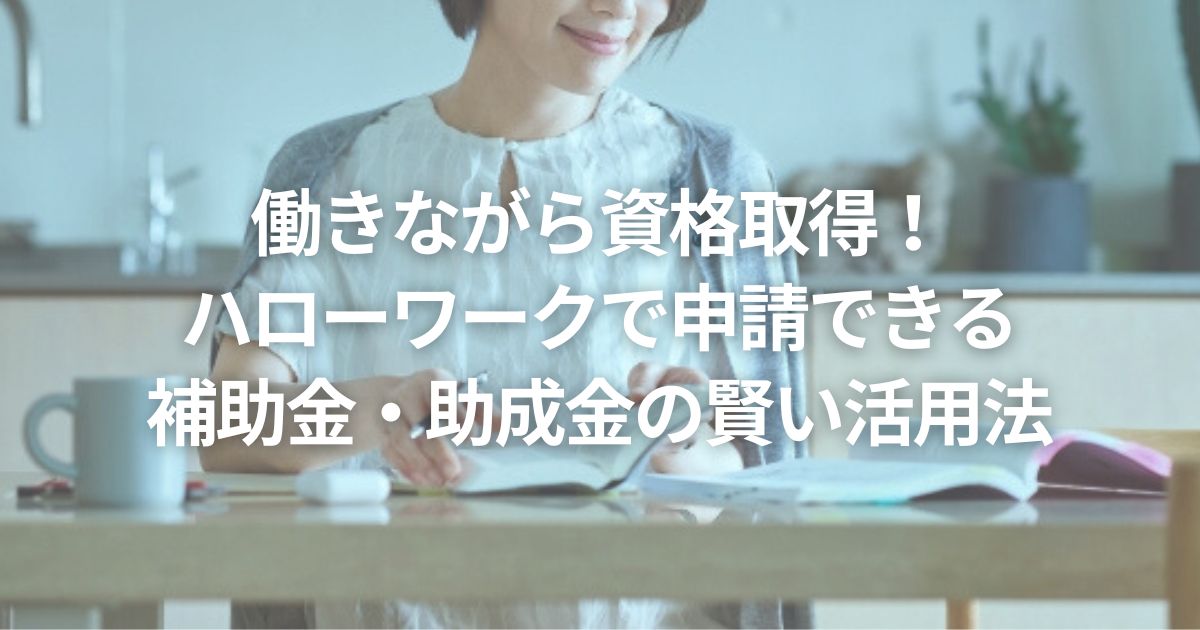
このまま働き続けて良いのだろうか・・
そんな漠然とした不安を抱えながら、毎日会社に通ってはいないでしょうか?
キャリアアップのために資格を取りたいと思っても、受講費用が高額で諦めてしまった人は少なくないのではないでしょうか。
実は、国が提供する補助金・助成金を活用すれば、資格取得の費用負担を大幅に減らすことができます。
しかも、働きながらでも申請可能な制度がたくさんあり、2024年10月からは給付率も大幅にアップしています。
この記事では、会社員が個人で申請できる補助金・助成金の種類から具体的な申請方法や受給条件までを順を追って解説します。
 ウリ
ウリあなたのキャリアを変える第一歩を、今日から踏み出しましょう。
働きながら使える資格取得の補助金・助成金とは?
補助金と助成金の違いを理解しよう
まず、補助金と助成金の違いを正しく理解しておきましょう。
補助金は予算に限りがあり、審査があるため必ず受け取れるわけではありません。
その一方、助成金は定められた条件を満たせば原則として受給できる制度です。
会社員が個人で資格取得のために申請する場合、多くはハローワーク(公共職業安定所)が窓口となる教育訓練給付金を利用します。
雇用保険に加入している会社員なら誰でも申請できる可能性があり、働きながらキャリアアップを目指す人にとって非常に心強い制度です。
なぜ今、国は資格取得を支援しているのか
近年、国が資格取得支援に力を入れている背景には3つの理由があります。
- リスキリング(学び直し)の推進
- 人材不足業界への人材誘導
- 個人のキャリア自律を促す社会の流れ
1つ目は、リスキリング(学び直し)の推進です。
技術革新が急速に進む現代社会では、一度身につけたスキルだけでは対応しきれない場面が増えています。
特にDXの波により、新しいスキルの習得が求められる時代になっています。
2つ目は、人材不足業界への人材誘導です。
介護や看護、IT、建設など、慢性的な人材不足に悩む業界への転職を促進するため、これらの分野の資格取得には手厚い支援が用意されています。
3つ目は、個人のキャリア自律を促す社会の流れです。
終身雇用制度が崩れつつある中で、一つの会社に依存せず自分自身で市場価値を高めていく「キャリア自律」の重要性が叫ばれています。



終身雇用も崩壊しつつある今、老後資金はキャリアアップして自力で準備して欲しいという政府の意図も透けて見えますね・・
ハローワークで申請できる主な制度3選
教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)
一般教育訓練給付金は、最も利用しやすい制度の一つです。
幅広い資格や講座が対象となっており、多くの会社員が活用しています。
対象となる資格・講座の例
- 簿記検定(2級・3級)
- TOEIC、英検などの語学資格
- 宅地建物取引士
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
- 介護職員初任者研修
支給額は受講費用の20%(上限10万円)です。
例えば、5万円の講座を受講した場合は1万円が戻ってきます。
主な受給条件は、雇用保険に1年以上加入していることです ※初回利用の場合。
在職中はもちろん、離職後1年以内であれば申請可能です。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ資格が対象で、2024年10月から給付率が40%から50%に引き上げられました。
対象となる資格の例
- 税理士、社会保険労務士などの士業
- 大型免許、中型免許などの運転免許
- 介護福祉士実務者研修
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- デジタル関連の講座(プログラミング、データサイエンスなど)
支給額は受講費用の50%(上限25万円)です。
さらに、資格取得後に就職等した場合、受講費用の10%(上限5万円)を追加で支給されます。
ただしこの制度を利用するには、受講前にハローワークでキャリアコンサルティングを受けることが必須です。



ハローワークでのキャリアコンサルティングの予約は混み合うので、スケジュールに余裕を持って早めに取ることをおすすめします。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は3つの制度の中で最も支給額が大きく、2024年10月から給付率が最大70%から80%に引き上げられました。
対象となる資格の例
- 看護師、准看護師
- 美容師、理容師
- 保育士
- 調理師
- 専門職大学院(MBA、法科大学院など)
- 情報処理技術者試験関連の長期講座
- キャリアコンサルタント
支給額は受講費用の50%(年間上限40万円)が基本です。
資格取得後に被保険者として雇用された場合は追加で20%(年間上限16万円)が支給され、さらに受講後に賃金が5%以上上昇した場合は追加で10%(年間上限8万円)が支給され、合計で最大80%の支援を受けられます。
最長3年間の受講が対象となるため、最大で192万円の給付を受けることも可能です。
受給条件は、雇用保険の加入期間が3年以上(初回は2年以上)と、他の制度より長めに設定されています。
その他の活用できる補助金・助成金制度
自治体独自の資格取得支援制度
ハローワークの制度以外にも、各自治体が独自に設けている資格取得支援制度があります。
地域によって内容が大きく異なるため、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認するのがおすすめです。
例えば、東京都では介護職員の資格取得を支援する制度や、保育士資格取得のための支援制度などがあります。
大阪府では、IT関連資格の取得支援や、看護師・介護福祉士を目指す人への奨学金制度などがあります。
自治体の制度は国の制度と併用できる場合もあるため、二重に申請することで負担をさらに軽減できる可能性があるので、ぜひ調べてみてください。



ハローワークで補助金や助成金について相談する際に合わせて聞いてみるのが良いかもしれないですね。
人材開発支援助成金(事業主経由)
人材開発支援助成金は主に企業が従業員のスキルアップのために活用する制度ですが、会社を通じて個人も恩恵を受けることができます。
会社員の立場からは、会社に「この資格を取りたいので、人材開発支援助成金を活用してもらえないか」と相談するカタチになります。
業務に直結する資格や会社が推進している分野のスキルであれば会社側も前向きに検討してくれる可能性が高まるので、こちらの方法もおすすめです。
補助金・助成金を受け取る条件とは?
共通する基本的な条件
各制度には細かな違いがありますが、ほとんどの制度に共通する基本的な受給条件があります。
- 雇用保険の加入期間
- 在職中または離職後1年以内
- 指定された教育訓練講座であること
最も重要な条件は、雇用保険に一定期間以上加入していることです。
一般的には1年以上、専門実践教育訓練給付金では2〜3年以上の加入が必要です。
また、基本的には在職中に申請するケースが多いですが、離職後でも1年以内であれば申請できます。
注意点としましては、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座でなければ給付金の対象になりません。



厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索できますので、一度確認してみることをおすすめします。
申請前に確認すべきチェックリスト
申請をスムーズに進めるために、以下の項目を事前にチェックしておきましょう。
□ 自分が雇用保険に加入しているか
□ 雇用保険の加入期間が条件を満たしているか
□ 受講したい講座が指定講座に該当しているか
□ 過去に給付金を受給したことがあるか
□ 受講開始日と申請期限の関係を理解しているか
□ 必要書類が揃っているか
特に重要なのは、受講開始前に手続きが必要な制度が多いということです。
受講を開始してから給付金があったと気づいても、遡って申請することはできませんので注意しましょう。
補助金・助成金の具体的な申請方法
まずは、最寄りのハローワークを訪れて、自分が給付金を受給できる資格があるか確認しましょう。
持参すべき書類
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印で可)
窓口で「教育訓練給付金について相談したい」と伝えれば、担当者が対応してくれます。
キャリアコンサルティングの活用
特定一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金を利用する場合は、キャリアコンサルティングを受けることが必須です。
この面談を通じて「ジョブ・カード」を作成します。
受給資格があることが確認できたら、次は具体的にどの講座を受講するか決めます。
厚生労働省のウェブサイトにある「教育訓練講座検索システム」を活用しましょう。
給付金の種類、資格の分野、受講形態、地域、受講期間などの条件で検索できます。
資格選びで重要なのは、自分のキャリアに役立つ資格を選ぶことです。
仕事で活かせるか、転職市場で価値はあるか、自分の興味・関心と合うかなどを考慮しましょう。
講座が決まったら、受講開始前に必ず申請手続きを行います。
申請期限に注意
- 一般教育訓練給付金:原則として申請不要(受講修了後に支給申請)
- 特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金:受講開始日の1か月前までにハローワークで手続き
必要書類の準備リスト
- 教育訓練給付金支給要件照会票
- ジョブ・カード(特定一般・専門実践の場合)
- キャリアコンサルティング実施証明書(特定一般・専門実践の場合)
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
講座を受講して無事に修了したら、いよいよ給付金の支給申請です。
修了日の翌日から起算して1か月以内に、ハローワークで支給申請を行います。
この期限を過ぎると給付金を受け取れなくなるので、修了したらすぐに手続きしましょう。



申請が受理されますと、通常は1〜2か月程度で指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。
【コラム】知っておきたい!サラリーマンも使える「特定支出控除」で資格取得費を節税
実は、サラリーマンでも資格取得費用を経費として計上できる「特定支出控除」という制度があることをご存知でしょうか。
これは、仕事に関連して自己負担した経費について、確定申告をすることで給与所得から控除できる制度です。
対象となる支出
資格取得費、研修費、図書費、勤務用の衣服費、接待費など最大7項目が対象です。
特に資格取得費は、弁護士や公認会計士、税理士などの資格試験予備校や法科大学院の費用なども含まれます。
控除を受けられる条件
特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超えた場合に、その超えた部分が控除されます。
例えば、年収400万円の人は給与所得控除額が約134万円なので、その半分の67万円を超える特定支出があれば、超えた分が控除対象です。
2023年度からの改正ポイント
令和5年度の税制改正で、厚生労働大臣指定の教育訓練給付講座を受講する場合、研修費と資格取得費は会社の証明に代えてキャリアコンサルタントによる証明でも申請できるようになりました。
これにより、会社に知られずに申請しやすくなっています。



確定申告が必要ですが、高額な資格取得を考えている方は検討する価値があるでしょう。
補助金・助成金活用の成功事例
ケース1:30代会社員が簿記2級を取得してキャリアチェンジ
営業職として働いていたAさん(35歳・男性)は、経理職への転職を考え、簿記2級の取得を決意しました。
通学講座の受講料は約10万円でしたが、一般教育訓練給付金を活用することで2万円が支給され、実質8万円の負担で済みました。
週2回の夜間講座に半年間通って無事に簿記2級に合格し、その後中小企業の経理職に転職して年収も50万円アップしています。
ケース2:40代会社員がITエンジニアへ転身
事務職として働いていたBさん(42歳・女性)は、プログラミングの学習を決意しました。
専門実践教育訓練給付金の対象となるオンラインプログラミングスクール(1年コース、受講料72万円)を選択し、給付金で最大58万円(約80%)が支給される可能性もあり、大幅に負担を軽減できました。
平日夜と週末を利用してオンライン学習を進め、修了後、IT企業の社内エンジニアとして採用されています。
よくある質問(Q&A)
- 会社に知られずに申請できますか?
-
基本的には可能です。
教育訓練給付金は個人がハローワークで申請する制度なので、会社に通知が行くことはありません。
給付金の申請に会社の許可や書類は不要です。
- すでに受講を開始してしまった場合は?
-
残念ながら、遡っての申請はできません。
特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は、受講開始日の1か月前までに申請が必要です。
- 不合格だった場合でも給付金はもらえる?
-
講座を修了していれば、多くの場合は給付金を受け取れます。
教育訓練給付金は基本的に「講座を修了すること」が条件であり、必ずしも資格試験に合格することが条件ではありません。
- 複数の制度を併用することは可能?
-
国の制度同士の併用は基本的にできませんが、自治体の制度との併用は可能な場合があります。
自治体によって併用の可否は異なるので、両方の制度に申請する前に確認することをおすすめします。
- 離職後でも申請できますか?
-
離職後1年以内であれば申請可能です。在職中だけでなく、離職後でも受給可能です。
転職活動中に資格を取得してスキルアップしたい場合に活用できます。
まとめ:補助金・助成金の活用で新しいキャリアへの一歩を踏み出そう!
この記事のポイントを下記にまとめました。
- 国の制度を使えば、費用負担を大幅に軽減できる
- 教育訓練給付金を活用すれば、受講費用の20%〜80%が支給されます。
- 2024年10月からは給付率も大幅にアップしています。
- 働きながらでも申請可能
- 在職中、離職後を問わず申請でき、夜間講座やオンライン講座も対象です。
- まずはハローワークで相談を
- 自分が受給資格を持っているか、どの制度が適しているかは、ハローワークで確認できます。
- 受講開始前に必ず相談しましょう。
- 資格取得は将来への投資
- 資格取得によって転職や昇給のチャンスが広がります。
- 長期的な視点で考えれば、大きなリターンが期待できます。
- 行動を起こすことで、選択肢が広がる
- 「このままでいいのか」と悩んでいるだけでは何も変わりません。
- まずは情報収集から始め、小さな一歩を踏み出してみましょう。
上記を踏まえた上で、今日からできるアクションとしては・・
- 最寄りのハローワークの場所と営業時間を調べる
- 取得したい資格や興味のある分野をリストアップする
- 厚生労働省の教育訓練講座検索システムで対象講座を調べる
- 雇用保険被保険者証を探して、加入期間を確認する
キャリアに悩んでいる時間は、決して無駄ではありませんし、その悩みは新しい自分に出会うためのサインかもしれません。
補助金・助成金という強い味方を得て、あなたも理想のキャリアへの第一歩を踏み出してみませんか?
